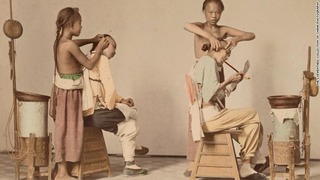ハワイで毎週50万匹の「蚊」を上空から投下、その狙いは
(CNN) ハワイの森に今年6月、上空のドローン(無人機)から生分解性の容器数十個が投下された。それぞれの容器には約1000匹ずつの蚊が入っていた。
ただの蚊ではない。実験室で飼育された刺さないオスの蚊で、「ボルバキア」という細菌に感染している。感染したオスが野生のメスと交尾して産まれた卵は孵化(ふか)しない。蚊の繁殖を阻害することで、ハワイミツスイなど現地の鳥類を絶滅から救うのが狙いだ。
ハワイミツスイは花粉や種子を運ぶ重要な役割を担い、ハワイの文化にも大きな位置を占める。かつてハワイに50種以上生息していたが、現在残るのは17種で、その大部分が絶滅の危機にある。
ハワイミツスイの一種で小さな灰色の鳥「アキキキ」は昨年、生態系での役割を失う「機能的絶滅」に陥った。黄緑色の「アケケエ」は、生息数が100羽を切ったと推定される。
開発や森林伐採の影響もあるが、米鳥類保護協会(ABC)ハワイ担当責任者のクリス・ファーマー氏が「存続にかかわる脅威」と呼ぶのは、蚊が媒介する鳥マラリアだ。
約1000匹の蚊が入った容器を投下するドローン
ハワイの蚊は捕鯨船が偶然持ち込んだとみられる外来種で、1826年に最初に報告された。その後、ハワイミツスイなど鳥マラリアへの免疫がない在来鳥類の多くは次々に絶滅したと、ファーマー氏は説明する。
同氏によると、蚊はハワイ諸島の中でも気温の高い低地で繁殖するため、生き残ったハワイミツスイはマウイ島やカウアイ島の高山へ逃れた。だが気候変動で気温が上昇し、近年は山の上でも蚊がみられるようになった。その結果、カウアイ島などでは鳥が激減しているという。
蚊の生息地が高くなるにつれて鳥はさらに上へ上へと追いやられ、ついには生息できる場所がなくなってしまう。同氏は「このサイクルを破らなければ、私たちはハワイミツスイを失うことになる」と警告した。
解決策を求めて
専門家らは蚊の数を制御し、ハワイミツスイを救うための方策を探し求めてきた。だがファーマー氏によれば、広範囲に対策を講じるのは難しい。例えば殺虫剤を使うと、現地の生態系に不可欠なイトトンボやショウジョウバエなど在来種の昆虫に害を及ぼす恐れがある。
蚊は人間にとってもマラリアやデング熱、ジカ熱などの感染症を媒介する健康上の脅威とみなされ、何十年も前から対策が研究されてきた。
そのひとつが、ボルバキアを使って卵に「細胞質不和合」を起こさせ、孵化を阻止する「不適合昆虫技術(IIT)」だ。
ABCは2016年、ハワイミツスイの保護に取り組む多機関パートナーシップ「バーズ・ノット・モスキートーズ」と共同で、鳥マラリアを媒介するハワイの蚊にIITを適用する方法の検討に乗り出した。
ファーマー氏によると、鳥マラリアを運ぶ蚊は人間のマラリアを媒介する蚊と種類が異なるため、まずボルバキアのどの株が最も有効かを試す研究に着手した。
こうした研究や地域社会との話し合い、規制当局への手続きに数年間を費やした。ファーマー氏は「森に数百万匹の蚊を放ちたいと言い出せば、住民から多くの質問を受けるのはごく当然のことだ」と振り返る。
22年には米カリフォルニア州の実験室で、選定したボルバキア株を持つ蚊の飼育が本格化。翌年から、この蚊を容器に入れ、ヘリコプターでマウイ島に投下する作業が始まった。生息する蚊の数を大まかに推定し、その10倍の数を放つことにしたという。
カウアイ島の固有種「アケケエ」
ファーマー氏によると、現在はドローンとヘリを使い、マウイ島とカウアイ島にそれぞれ毎週50万匹を投入している。
同氏によれば、環境保全の目的にIITを適用した例は世界初。ハワイ以外の場所でも対策のヒントになりそうだ。ただし、ハワイの蚊は約200年前からの外来種で生態系に大きな役割を果たしていないのに対し、在来種の蚊がいる国々ではIITが生態系に予期せぬ影響を及ぼす可能性もある。
時間稼ぎの手段として
ハワイでの大きな課題は、山の多い地形や強風などの変わりやすい天候だ。投下に使うヘリは運航経費が高く、消火、救助活動や観光との共用で数も限られている。
そこで6月からドローンが導入された。天候の変わりやすい地域でも飛行のタイミングを柔軟に選ぶことができ、無人なので安全性も高い。経費や排ガス、騒音も抑えられる。
ファーマー氏によれば、IITが有効かどうかの結果が出るまでには1年ほどかかる見通し。だが同氏は、ハワイミツスイの回復に向けて「時間を稼ぐ」効果に期待を寄せる。
蚊の数が抑制されれば、ハワイミツスイが生息数を補い、遺伝子の多様性を高める時間ができる。鳥マラリアへの耐性を持つようになるかもしれない。ファーマー氏によると、ハワイ島に生息するハワイミツスイの仲間「アマキヒ」には、すでにその兆候がみられるという。
生息環境が安全になれば、ハワイの保全センターで人工飼育されているアキキキのような種類を野生に再導入するチャンスも期待できそうだ。
ファーマー氏は「この10年のうちに私たちが救わなければ、ハワイミツスイは恐らく永遠にここからいなくなる。世界に、そして将来に変化をもたらすことが、私たち全員のモチベーションだ」と話している。