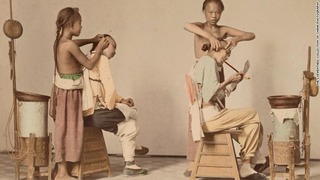地球の自転速度が上昇、「うるう秒」めぐり前代未聞の対応が必要か
(CNN) この夏、地球の自転の速度が速くなって1日の時間がわずかに短くなったことが科学者や時間の管理を行う人たちからの注目を集めている。
今月10日は今年に入って最も短い1日となり、24時間よりも1.36ミリ秒短かった。この数字は、「timeanddate.com」がまとめた国際地球回転・基準系事業(IERS)と米海軍天文台のデータによるものだ。さらに異常に短い日が8月5日にも訪れ、1.25ミリ秒短い日になると予測されている。
1日の長さは地球が自転軸を中心に1回転するのにかかる時間で、平均すると24時間、つまり8万6400秒だ。しかし、実際には、月の引力や大気の季節の変化、地球の液体核の影響などさまざまな要因によって、自転周期はわずかに不規則となっている。そのため、1回転にかかる時間は通常8万6400秒よりわずかに短いか長いかだが、これはわずか数ミリ秒の差であり、日常生活に明らかな影響を及ぼすものではない。
だが、こうしたずれは長期的にはコンピューターや衛星、通信に影響を及ぼす可能性があるため、1955年に導入された原子時計を使って、たとえわずかな時間のずれであっても追跡が行われている。専門家のなかには、これが現代文明を停止させる恐れがあった「2000年問題」に似たシナリオにつながる可能性があると考える人もいる。
原子時計は時計内部の真空容器に閉じ込められた原子の振動を数え、極めて高い精度で24時間を計算する。その時間は協定世界時(UTC)と呼ばれる。UTCは世界標準時として、すべての携帯電話やコンピューターの時刻設定の基準となっている。

ドイツ物理工学研究所の原子時計/Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa/Getty Images
天文学者は地球の自転も追跡している。例えば、恒星に対する地球の位置を確認する衛星などを用いて、原子時計の時刻と地球が実際に1回転するのにかかる時間との間のわずかな差を検出することができる。2024年7月5日は、地球は原子時計の登場以降で、最も短い1日を経験した。この日は24時間より1.66ミリ秒短かった。
「1972年以降、1日がやや早くなる傾向にある」。スクリップス海洋研究所の地球物理学名誉教授で、カリフォルニア大学サンディエゴ校の地球物理学研究者のダンカン・アグニュー氏はそう語る。「しかし、変動はある。まるで株式市場を見ているようだ。長期的な傾向があり、その後、最高値がつき、下落する」
72年、地球の自転が数十数年にわたって比較的ゆっくりと回転していたため、原子時と比べて遅れが生じ、IERSはUTCに「うるう秒」を追加することを義務付けた。うるう秒は、グレゴリオ暦と地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間との間のずれを補うために、4年ごとに2月に1日を追加する「うるう年」に似ている。
72年以降、UTCには合計27回のうるう秒が追加されたが、地球の速度が高まったことで、うるう秒が挿入される頻度は徐々に遅くなっている。70年代を通じて9回、うるう秒が追加されたが、2016年以降はうるう秒は追加されていない。
22年、国際度量衡総会(CGPM)は35年までにうるう秒を廃止することを決議した。つまり、今後、時計にうるう秒が追加されなくなる可能性がある。だが、アグニュー氏によれば、地球の自転速度が今後数年速くなり続けると、最終的にはUTCから1秒を削除する必要が出てくるかもしれない。アグニュー氏は「これまではマイナスのうるう秒は発生していないが、今から35年までの間に発生する確率は約40%だ」との見方を示した。
自転が速くなる原因は
アグニュー氏によれば、地球の自転の最も短期的な変化は月と潮汐(ちょうせき)で、月が赤道上にあるときは回転速度が遅くなり、高度が高い時や低いときは回転速度が速くなる。こうした効果に、夏の間は地球が自然に速く回転するという事実が加わる。これは南北に移動するジェット気流などの季節変化により大気自体が減速する結果だ。物理法則により、地球とその大気の全体的な角運動量は一定に保たれなければならないため、大気によって失われた回転速度は地球自体によって補われる。同様に、過去50年間、地球の液体の核は減速し、その周囲の固体の地球は加速してきた。
これらの影響の組み合わせを観察することで、将来の1日が特に短くなるかどうかを予測できるようになる。国立標準技術研究所の研究員で物理学者のジュダ・レバイン氏は「これらの変動は短期の相関関係があり、地球がある日に速度を上げていたら、次の日も速度を上げる傾向があることを意味する」と指摘した。「だが、その相関関係は観測期間が長くなるにつれて消えていく。そして、1年になると予測は非常に不確実になる。実際、IRESは1年以上先の予測は行わない」

地球の自転速度は月などさまざまな要因の影響を受けている/NASA
レバイン氏によれば、1日短いだけでは何も変わらないが、最近の1日が短くなる傾向によって、マイナスのうるう秒が発生する可能性が高まっている。「72年にうるう秒の制度が定義されたとき、マイナスのうるう秒が発生するとは誰も思っていなかった。完全性を保つために、単に標準に組み込まれただけだ。誰もがプラスのうるう秒だけが必要になると考えていたが、今では1日が短くなっているため(マイナスのうるう秒が)発生する危険性があると言える」
マイナスのうるう秒は懸念材料だ。レバイン氏によれば、50年経った今でも、プラスのうるう秒に関する問題が依然として続いているためだ。「いまだに、間違った方法で実施したり、間違った時間に実施したり、間違った数字で実施したりする場所がある。しかも、これはプラスのうるう秒に関する問題で、何度も繰り返されてきた。マイナスのうるう秒については、これまで一度もテストしたこともやってみたこともないため、はるかに大きな懸念だ」
溶ける氷の役割
気候変動も、うるう秒問題の一因となっているが、その影響は意外な形で表れている。地球温暖化は地球に相当な悪影響を及ぼしてきたが、時間管理という点では、地球の自転を加速させる力を打ち消す役割を果たしてきた。アグニュー氏が昨年ネイチャー誌に発表した研究によれば、南極とグリーランドの氷が融解して海上に広がり、地球の自転速度を低下させた。
アグニュー氏は「もし氷が溶けていなかったら、地球温暖化が起こっていなかったら、我々はすでにマイナスのうるう秒を経験していたか、あるいは、それに非常に近いところまできていただろう」と述べた。米航空宇宙局(NASA)によれば、グリーンランドと南極の氷床から溶けた水は1993年以降の世界の海面上昇の3分の1を占めている。

南極やグリーランドの氷が溶けて、地球の自転速度に影響を与えている/Sebnem Coskun/Anadolu Agency/Getty Images