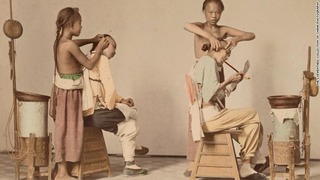ヒトゲノムに取り込まれた古代ウイルスのDNA、人間の進化に重要な役割か
古代ウイルスが人類の進化に及ぼした影響
研究チームは、霊長類のゲノムにみられる「MER11」というTE配列に着目した。新たな分類法を開発してDNAの活動を調べたところ、未知の小グループが四つ見つかった。
組み込まれた時期が最も新しい「MER11―G4」という配列は、人間の幹細胞と初期の神経細胞の遺伝子発現を促す強い能力を備えていることが分かった。京都大学の声明によると、この小グループが人間の初期の発達に関与し、遺伝子が発達シグナルや環境の刺激にどう反応するかを大きく左右し得ることがうかがえる。
また、ウイルス由来のTEは人類がどう進化するかの道筋に関与したことも示唆された。DNAが時とともに変化した経緯をたどった結果、この小グループが異なる動物のゲノムでそれぞれ異なった進化を遂げ、ヒトやチンパンジー、サルの分岐に寄与したことが分かった。
「ヒトゲノムの進化を理解することは、人間をほかの動物と区別しているのは何かを理解する道のひとつだ」と、ホー氏は言う。
チェン氏によれば、具体的にTEが進化の過程にどうかかわったのかは依然として不明。まだ見つかっていないほかのTEが、霊長類の進化過程で別の役割を果たした可能性もあるという。
本研究にかかわっていない独ライプニッツ老化研究所のスティーブ・ホフマン氏は、かつてがらくたと軽視されたDNAから、学ぶべきことがどれだけあるかが浮き彫りにされたと指摘した。
ゲノムがどう進化してきたかを調べることで、どのDNA配列がそのまま残り、どれが時とともに消え、どれが最も新しいかを判別することができる。
「こういう配列を考慮に入れることは、例えば人間がほかの動物にみられない病気にかかるのはなぜか、その理由などを把握するうえで不可欠だ」と、ホフマン氏は説明。「最終的に、ゲノム制御をより深く理解すれば、新たな治療法や医療行為の発見が促される可能性がある」と述べた。