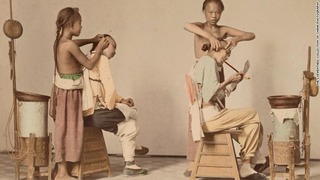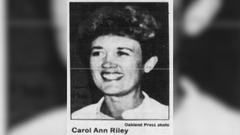太陽系通過する3個目の恒星間天体、前例ない鮮明さの画像を公開
(CNN) 太陽系内を猛スピードで移動する新発見の天体について、これまでで最も鮮明な画像が公開された。
ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された広視野カメラ3が見事にその姿を捉えた天体は、「3I/ATLAS」と名付けられた彗星(すいせい)。太陽系外から飛来し、先月21日には地球から4億4500万キロの距離にあった。
今回の画像には彗星周辺の塵(ちり)が凍った核の部分から涙滴状に伸びる様子が写っている。核は固体で、氷と塵、岩石でできている。彗星が太陽のような恒星の近くを通過する場合、熱によってガスや塵が放出され、彗星特有の尾を形成する。
最初に発見された7月1日、3I/ATLASは時速20万9000キロで移動しており、太陽系内を通過する系外からの天体としてはそれまでの最高速度を記録した。
ハッブル宇宙望遠鏡を用いた今回のような観測から、これまでよりも具体的な彗星の大きさが判明した。直接目視できない小さな核の直径は最大で5.6キロ、最小で305メートルだとみられる。天体物理学誌アストロフィジカル・ジャーナル・レターズに寄せられた論文で明らかになった。
一方、他の宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡によって、彗星の化学的組成についてもより多くのことが分かる可能性がある。彗星は9月を通じ地上の望遠鏡で観測できる見通しだが、その後は位置が不明になるほど太陽に近づき、12月初旬には太陽の反対側に再び姿を現す。
7月初旬に欧州宇宙機関(ESA)が「3I/ATLAS」を観測した際の動画
それでも3I/ATLASを巡っては、具体的に宇宙のどこからやって来たのかといったいくつかの大きな疑問が依然として残る。
動きこそ太陽系由来の他の彗星と似通っているものの、3I/ATLASの速度は銀河系に位置する他の恒星系から飛来した天体であることを示唆する。
科学者らは3I/ATLASが恒星間空間を数十億年移動していると推計している。天体が宇宙空間を移動すると、恒星や星の形成領域である育星場の重力から運動エネルギーを得る「スリングショット効果」によって速度が増す。従って3I/ATLASが長く宇宙空間を移動すれば、その分だけ移動速度は上がることになる。
3I/ATLASより前に太陽系内でこれまで観測された恒星間天体は2017年の「オウムアムア」 と19年の「2I/ボリソフ」のみ。
3I/ATLASの年齢を特定することは難しいが、研究者らは67%の確率で76億歳を超えるとみている。これに対し、太陽及び太陽系、そしてその系内の彗星はまだ45億歳だという。