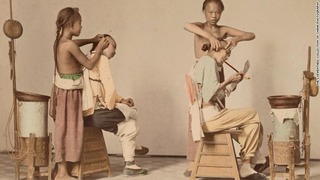新たに命名された太古のセミの化石、保存状態良く翅脈もくっきり
(CNN) 一片の岩に平面となって押しつけられているのは、4700万年前に生息していた1匹のセミだ。体長は約2.7センチ、左右の羽から羽までの長さは6.8センチ。ほぼ無傷の化石で、広げた羽に走る翅脈(しみゃく)も確認できる。
科学者らは最近、このセミが新種であることを突き止めた。当該の化石の他、同じ現場で見つかった同様に保存状態の良い別の化石も使って判断した。これらの化石は雌だが、セミの系統樹が示唆するところによればこの種の雄は現在のセミのように鳴くことが出来たとみられる。数十年前にドイツでこれらの化石が見つかったことで、鳴く種類のセミは従来考えられていたより数百万年早く欧州に分布していたことが明らかになった。
化石のセミに関する報告は、先月29日付のサイエンティフィック・リポーツ誌に掲載された。
現在のセミには数多くの種類が存在するが、古生物学者がこれまで記録したセミの化石は44点のみ。論文の筆頭著者であり、独ボン大学有機体生物学研究所に在籍する古生物学者のフイ・ジャン博士によると、鳴くセミと確定した化石で最古とされるのは、米モンタナ州で発見された5900万~5600万年前の化石だという。今回新たに特定された化石のセミは、鳴くセミとして欧州で最も古い種だと、ジャン氏はCNNに電子メールで明らかにした。
従来、この系統のセミはアフリカで3000万~2500万年前に進化し、そこから各地へ分布したと考えられていた。今回の発見で、確認される最古の化石の年代は約2000万年古くなったと、ジャン氏は説明する。

新たに命名された太古のセミ「Eoplatypleura messelensis」の再現画像/Dinghua Yang
当該の化石は1980年代、化石が豊富に見つかることで知られるドイツのメッセル採掘場で発見された。 研究者らは採掘場の名にちなみ、このセミをEoplatypleura messelensisと命名した。かつては深い火山湖の底にあり、酸素が入り込まなかったこの採掘場は、生物が化石化する上で理想的な環境だった。独ゼンケンベルク研究所・自然史博物館で古生物学部門を統括するソニア・ベドマン博士は、CNNの取材に電子メールでそう答えた。
昆虫だけでなくあらゆる有機物が極めて良好な状態で保存されているため、メッセル採掘場は95年にユネスコの世界遺産に登録されたと、ベドマン氏は付け加えた。
頭部全体と体形に関して、E.messelensisは現在のセミに酷似している。体色や羽の模様も、現在のセミの保護色のように機能していた可能性がある。
しかし細かい点では違いもある。例えば前翅は現在のセミよりも幅が広くて短い。これは飛び方に影響を及ぼしていた可能性がある。
鳴き声はどうか? 前出のジャン氏は正確な鳴き声は分からないとしつつ、その体形や鳴くセミの系統内の位置づけから、現在のセミと似た音を鳴らしていた公算が大きいと述べた。
音量は太古のセミの方が大きかったかもしれないとジャン氏。E.messelensisの腹部は現在の同種のセミより幅があって大きい。従って雄の腹部にある共鳴室もより大きかった可能性があると考えられるという。
ただこれはあくまでも仮説に過ぎず、形態学と音の発生に関する将来の研究で検証が進むだろうと同氏は付け加えた。