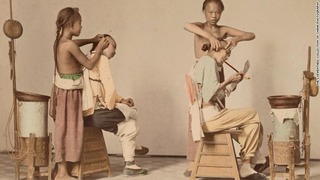始祖鳥の飛行の秘密、希少な化石の分析で明らかに 研究者「驚きの連続」
(CNN) 研究者らは長年、始祖鳥がどのように空へ舞い上がったのか疑問を抱いていた。羽毛のある恐竜は他にもいたが、そのほとんどは地上から離れようとしなかった。また始祖鳥は、恐らくどちらかと言えばグライダーのように風に乗っていたのであって、本当の意味で空を飛んだのではないと論じる研究者もいた。
このジュラ紀に生息した謎の有翼生物の化石がドイツ南部で初めて見つかったのは160年以上前。化石の年代は1億5000万年前だった。以後発見された始祖鳥の化石は14体のみで、その一部は民間の収集家が入手。科学的な研究が不可能になり、鳥類の進化における重要な時期に関する検証は妨げられてきた。
米シカゴのフィールド自然史博物館が最近入手した化石は、そうした始祖鳥の飛び方にまつわる長年の疑問に答えるものだった。研究者らが公表した化石の概要は14日付の科学誌ネイチャーに掲載された。ハトほどの大きさの化石標本を紫外線とCTスキャンで調べたところ、これまでの始祖鳥からは確認されなかった軟組織や構造が明らかになった。羽毛などに関するそうした発見は、始祖鳥が滑空ではなく自ら体を動かすことで空を飛んでいた可能性を示唆するものだ。
大半の始祖鳥の化石標本は「不完全で損傷している」が、この化石は足の指1本が欠けているだけで、年月による劣化もない。論文筆頭著者のジンマイ・オコナー氏はそう語る。同氏はフィールド自然史博物館で爬虫類(はちゅうるい)化石担当の学芸員を務める古生物学者。

紫外線の光を当てた始祖鳥の化石。骨格に沿った軟組織の存在が確認できる/Delaney Drummond/Field Museum
飛ぶための羽毛
推計で約1600時間をかけて化石を分析したところ、研究者らは始祖鳥については初めてとなる三列風切羽と呼ばれる羽の証拠を探り当てた。これは上腕骨に沿って肘(ひじ)と胴体の間に生える羽で、現在のあらゆる鳥類が自らの動きで飛行する際に重要な部位となる。1980年代以降科学者らは、上腕骨の長さから始祖鳥にも三列風切羽があったとする仮説を立てていたが、実際にそのような羽が見つかったのは今回が初めてだ。
驚きはそこで終わらない。口蓋(こうがい)の骨からは鳥類における頭骨の特徴の進化に関する手掛かりが得られた。この特徴とは頭部を構成する骨が相互に関連しながら独自に動くというもので、これにより鳥類はより柔軟に嘴(くちばし)を使うことができるようになっている。
化石の分析は「驚きの連続だった」と、オコナー氏は振り返る。
三列風切羽は特に並外れた発見で、それにより始祖鳥が実際に飛行可能だったことが示唆されるという。米サウスカロライナ州のクレムソン大学の生物学准教授、スーザン・チャップマン氏はそう指摘する。同氏は今回の調査に関与していないが、古生物学と発生生物学を駆使して鳥類の進化を研究している。
しかし恐らく始祖鳥が飛べたのは短い距離に限られただろうとチャップマン氏は述べた。三列風切羽はあるものの、現代の鳥類と異なり、飛行に特化した筋肉やそれを支える長い胸骨といった特徴がみられないためだ。

フィールド自然史博物館が2022年に入手した始祖鳥の化石は、情報がぎっしり詰まった「見事な」標本だった/Delaney Drummond/Field Museum
進化の転換点
飛ばない獣脚類の恐竜と現代の全鳥類の起源とをつなぐ存在として、始祖鳥の進化の重要性に疑問の余地はない。しかしオコナー氏に言わせれば、2022年に博物館が当該の始祖鳥の化石を入手したのは大きな賭けだった。化石は1990年から個人が所有しており、保存状態は不明。博物館に到着したときも、どのような研究成果が得られるのか科学者らには判然としていなかったという。
しかし実際にオコナー氏らの目の前に現れたのは、全く想像していなかったほどの見事な標本だった。
オコナー氏は恐竜から鳥類への進化について、地球の生命の歴史において最も重要な転換点の一つと位置づける。それは恐竜の一群が白亜紀末期の大量絶滅を生き延びただけでなく、そこから現在の地球上で最も多様な地上脊椎(せきつい)動物のグループへと変化を遂げたことを意味するからだ。これは極めて重要な進化の過程だという。
同博物館の始祖鳥には他にも鳥類の進化にまつわる重要な詳細が保存されている公算が大きいと、オコナー氏は言い添える。これまで化石から収集されたデータの豊富さや依然進行中の分析作業を踏まえれば、今後もさらに多くの発見があるに違いないと、同氏は期待を寄せている。