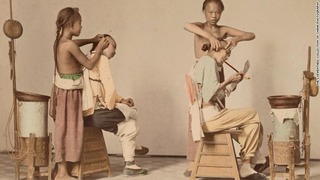ミイラの研究で判明、科学者も知らなかった18世紀の防腐処理法 オーストリア
(CNN) 人里離れたアルプス山脈の村の教会にある地下納骨堂に安置されていた、保存状態のすこぶる良い人間の遺体は、長らく様々な風説や臆測の的となってきた。
地元の伝承によると当該のミイラは、感染症で亡くなった18世紀の聖職者と考えられている。死後数年後に墓から掘り起こされ、オーストリアのドナウ川北岸の村にある聖トーマス・アム・ブラーゼンシュタイン教会の地下納骨堂に移されたとみられる。
皮膚や組織が無傷のまま奇跡的に保存されていた遺体は、当時から巡礼者たちを惹(ひ)きつけ、治癒の力があるのではないかと考えられていた。数世紀後にはミイラのX線調査でカプセル状の物体を発見したことから、聖職者がより悲惨な最期を遂げたのではないかとの見方が浮上した。つまり毒殺された可能性だ。
現在科学者チームは、「空気乾燥した聖職者」の異名を取る謎のミイラを巡り、多くの未解明の疑問に対する新たな知見を提供している。これらの発見のきっかけは、地下納骨堂の水漏れを直すための最近の改修工事だった。この工事のおかげで、科学者らは遺体に最先端の科学的分析を施すという思いがけない機会に恵まれた。
研究を率いた独ミュンヘンのルートビヒ・マクシミリアン大学医学教授、アンドレアス・ネルリッヒ氏と同僚たちは、CTスキャン、放射性炭素年代測定、骨と組織サンプルの化学分析を通じミイラの身元を確認。遺体の長期保存を可能にした独特の方法を解明することに成功した。研究者らは医学誌「フロンティアズ・イン・メディシン」に2日に掲載された論文で研究結果を報告した。
これまで知られていなかった防腐処理法

聖職者のミイラは正面にも背面にも切開の痕跡が見られない/Courtesy Andreas Nerlich
研究最大の驚きはCTスキャンの結果だった。ミイラの腹部と骨盤腔には、モミやトウヒの木片、リネン、麻、亜麻布などが詰め込まれており、中には繊細な刺繍(ししゅう)が施されたものもあった。さらに毒物学的分析を行ったところ、塩化亜鉛などの痕跡が検出された。
「体壁は完全に無傷だったので、これは全く予想外のことだった」とネルリッヒ氏は振り返った。
この一見矛盾する現象を説明するため、研究チームは、そうした物質がおそらく直腸から挿入されたとの仮説を立てた。そして現在では、ミイラを空気乾燥した状態に保つのはこれらの物質の混合物だと考えている。
木片と布が水分を閉じ込めた他、塩化亜鉛の乾燥効果で腸内の細菌量も減ったと考えられると、ネルリッヒ氏は述べた。
この防腐処理の方法は、古代エジプトで用いられた、より知られている方法とは異なる。後者は遺体の開腹が必須だった。この聖職者に見られる手法は過去に科学文献で報告されたことがないともネルリッヒ氏は付け加えた。
ただ同氏によれば、この手法は当時の文献にこそ記載されていないものの、18世紀には遺体の輸送や安置を目的とする保存のために広く用いられていた可能性があるという。
「空気乾燥した聖職者」が天然のミイラではないことは明らかだが、遺体の保存に塩化亜鉛が使用されたかどうかを断定するにはより詳細な分析が必要だと、伊ボルツァーノにある民間研究機関ユーラック・リサーチのミイラ研究所の上級研究員、マルコ・サマデッリ氏は述べた。
サマデッリ氏によると、ミイラからはよく知られた防腐剤であるヒ素も微量検出されたという。
ミイラの身元を解読

ミイラの内部から見つかった木片や布などの詰め物(左)と、左の骨盤の中から発見されたガラス球/Courtesy Andreas Nerlich
研究チームは、ミイラ化された遺体は、フランツ・クサーバー・シドラー・フォン・ローゼネッグのものであると結論付けた。この人物は貴族階級で、修道士を経て聖トーマス・アム・ブラーゼンシュタインの教区司祭を約6年間務めていた。
シドラーは1746年、教区司祭職に就いたまま37歳で亡くなった。地元住民の間では、ミイラはシドラーのものだという風説が流れていたが、研究によるとそれを裏付ける文書は存在していなかった。
放射性炭素年代測定の結果、遺体の死亡年は34年から80年の間と推定される。死亡年齢は30歳から50歳、最も可能性の高い年齢は35歳から45歳と示唆された。
長年喫煙習慣があった当該の聖職者は、毒殺されたわけではないと研究で判明した。聖職者は慢性結核を患っており、それが急性肺出血を引き起こして死亡した可能性があると研究者らは考えている。
ミイラの体内には、両端に穴の開いた小さなガラス球が発見された。これは防腐処理材に偶然閉じ込められたロザリオのビーズの一部である可能性がある。ネルリッヒ氏によれば、このガラス球は2000年代初頭のX線調査で捉えられた弾丸状の物体であり、その発見からカプセルによる毒殺の疑いが浮上したという。