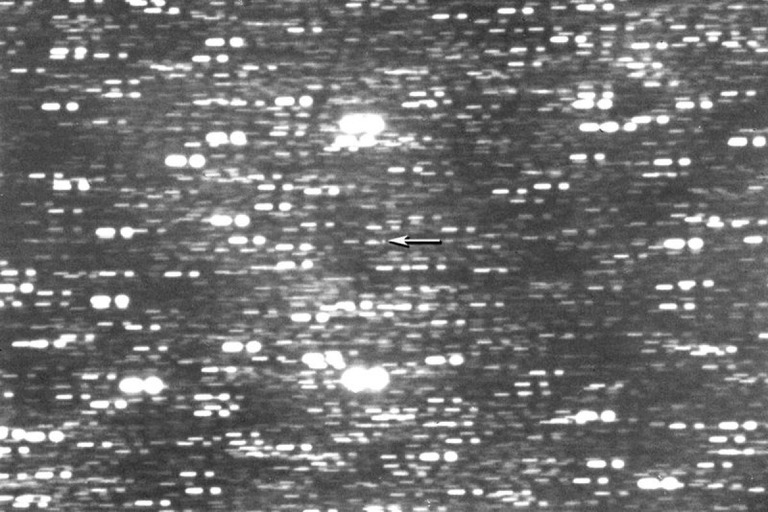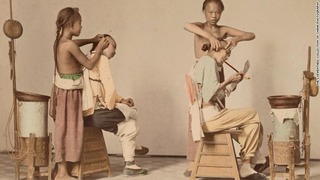太陽系内を猛スピードで移動する「恒星間天体」、天文学者が発見 3例目
(CNN) 太陽系内を猛スピードで移動する新たに発見された天体が、天文学者たちの間で興奮を巻き起こしている。太陽系外から飛来したことが判明したためだ。彗星(すいせい)とみられる天体は、太陽系内で観測された恒星間天体としてはわずか3例目となる。
この恒星間天体の正式名称は「3I/ATLAS」。米航空宇宙局(NASA)から資金提供を受けるチリのATLAS(小惑星地球衝突最終警報システム)望遠鏡が今月1日に発見を報告したことで、存在が知られるようになった。その後、複数の望遠鏡の観測データを精査した天文学者らは6月14日まで遡(さかのぼ)って天体の動きを追跡し、彗星がいて座の方向から到来したことを突き止めた。
彗星の速度と太陽系内での軌道は、太陽系外から到来したことを強力に示している――。イタリアのベラトリクス天文台の天体物理学者で、「バーチャル望遠鏡プロジェクト」の創設者兼科学ディレクターを務めるジャンルカ・マシ氏はそう説明する。
米ビラノバ大学のテディー・カレタ助教によれば、この彗星は秒速約60キロメートル、時速約21万4364キロで移動しており、太陽系内にある「ローカル」の天体としては速すぎるという。
カレタ氏は電子メールで、「太陽に縛られている天体、つまり太陽系内の天体は、太陽を周回して同じ地点に戻る軌道を取る」と指摘。 「地球の軌道はほぼ円形で、冥王星の軌道は引き伸ばされた楕円(だえん)だ。多くの彗星は『離心率』が非常に高く、軌道は非常に細長い楕円になる。今回の天体の太陽系内での進路は、ほとんど直線に近い」と述べた。
ESA/Las Cumbres Observatory
NASAジェット推進研究所の地球近傍天体研究センターで所長を務めるポール・チョダス氏は、天体の軌道を追跡することで、太陽系に到達した経路も明らかになると説明する。
チョダス氏はメールに「天体の移動を過去に遡って推定すると、明らかに太陽系外から到来したことが分かる」と記し、「別の太陽系から来たに違いない。おそらく何百万年にもわたって恒星間空間を旅していたところ、偶然、私たちの太陽系に遭遇したのだろう」と続けた。
この彗星の地球からの距離は6億7500万キロ。最初に発見されて以降、天文学者たちは世界各地の望遠鏡で競って観測を行っている。その一人がカレタ氏で、発見当日の夜に情報を得るとすぐさま、アリゾナ州のローウェル天文台にあるローウェル・ディスカバリー望遠鏡で彗星の観測を行った。カレタ氏は、あと2週間もすれば、地球上や宇宙空間にあるほぼすべての大型望遠鏡がこの彗星の観測に時間を割くようになるだろうとの見方を示す。

太陽系を通過する「3I/ATLAS」の軌道を示した図/NASA/JPL-Caltech
「みな興奮している。私の知る惑星天文学者はほぼ全員、すぐさま望遠鏡へ駆けつけるか、数日以内に望遠鏡の(観測)時間を申請するメールを送信した」とカレタ氏。「この魅力的な天体を研究する時間は数カ月あるかもしれないが、どのように進化しているか、どんな奇妙な予期せぬ特徴を持つかを早い段階で解明すれば、それだけ早いうちに太陽系を通過する残りの期間に備えることができる」